静かでのどかな緑多い街、元永。
春は眠りから覚めた「つくしんぼ」。
田はピンク色に染まったレンゲ草。
そばを流れる小川はメダカの学校。
初夏は辺り一面水を張った田が広がり、田植が始まる。
紫陽花が色濃く染まり、カエルの歌声が聞こえる梅雨の季節。
風に揺られる竹林の音、涼しい風が街を駆け巡る夏日。
そして黄金色した稲穂が輝き、刈り入れが始まる。
その香りが街中に広がり収穫の秋を迎える。
夕陽が朱色に染まる赤トンボの群れ。
静かにふけゆく秋の音色はコオロギ。
平尾台の山並みに薄っすらと雪景色。
スミ絵のような京築平野に、ほど良い寒さを覚える二月。
春夏秋冬まだまだ日本の故郷が残る元永を触てみたい
| 2006.開設した勇哲.洋子のポートフォリオ 1 2010.1.勇哲.洋子のポートフォリオ.2は、38リンク3500pリニュアルしました そして2017.7.より勇哲.洋子のポートフォリオ.3へ続き 新.2025.勇哲.洋子のポートフォリオ.4へ |


都会から離れて行橋市の東、周防灘に近い元永という街に住みついて早8年あまり。
この地で骨を埋めるつもりで、北九州市より引越して来た。
なぜ、この地に住むようになったかは、別ページを読んでいただくが、
この地の良さは、まず住まい。
次にのどかな自然と一望できる京都平野。
都会にないものがこの地にたくさんあることはまちがいないが、
住みついて分かる、その良さと、交流する人間味。
古き良き伝統、文化、庶民生活はその人々を
さらに人間らしく関われる事の面白さ、楽しさ、優しさ、想い、生甲斐。
そして人間模様をもう一度洗い流し原点を極めるとき、
自分を、私達を見つめる空間がここにある。
美しい、優しい自然美の中で一生を終えたい。
残り少ないタイムトラベルの中で一生懸命自分を表現してこのページを続けてみたい。
2008年7月 大和三郎丸 (上瀧勇哲)


京都平野、元永に引越し
勤めている会社が小倉から行橋に変わり、実家もおふくろさんが住んでいる行橋。
すぐ隣のみやこ町には弟も居て、
三兄弟そろって京築平野も良いかなァ?と想って家捜し。
ちょっと田舎で田ンボの中の一軒家。
150坪の敷地に鉄筋の家。
ちょっと良さそうだが古くさい。
階段がある玄関に家の中庭は畑になっているし。
かなりゴチャゴチャしている。
しかし、妻がえらく気に入り、これにしようと彼女が決めた。
大蔵大臣には従わなくてはならないので、ここに決めた。
そして借金でリフォーム。
三年後、国からの防音工事で再びリフォームで現在に至るが、
すごく立派になったと親戚皆から言われる。
その住まいをセンターにして、元永の街にとけ込む事8年余り。
今年は41軒の組長。
しかも180軒の区役員としての世話係。
ここから「おいらの街 元永」が始まった。

元永区制のしきたり
越して来てすぐ町内の役員が元永区(町内)に入会してくれと言って来たが、
私は入らないつもりで居た。
妻も前の希望ヶ丘自治会でイヤな想いをしたので断り続けた。
しかし隣近所から何度も誘われて、とうとう根負けし半年後に入会した。
ところがその後が大変。
区費、組費、神社、神幸費、おこもり、寄付、水利掃除に関わる会費がもの凄く必要で、
小倉のときの5~6倍も負担することになる。
しかも昔からの風習で、農家や神社との関わりが非常に多く、
こんなことなら入らなよかった。と随分後悔した。
これも近所付き合い、仕方なく妻が出て街のお付き合いをしてくれた。
もちろん私は仕事と趣味の世界に浸り、町内の行事等どうでも良かった。
そんなライフスタイルが7年余り続き、
今年は当番で組長になり41軒の世話をすることになった。
平成20年3月、前組長より引継ぎを行い4月よりスタート。
と想っていたら最初からつまづいてしまった。
それは元永区制を取り仕切る区長から会計等、10名ほどの人事を、
いきなりの組長12名から選出され自分達で決める仕組みに驚いた。
1年間、区の世話係及び組長を勤めて終わりなのだが、
分けの分かぬ私が区の役員に無理やりやらされることに不信感を抱いた。
もちろんその仕組みを知っている古くからの住人が受け継ぐのは良いが、
私のような転入者は困る。
しかも、この地は古くからのしきたりとか農家、水利、神社等との関わりが非常に多く、
色々なトラブルは避けて通れないほど数あることを前組長から知らされていたので、
新区長選出から役員を決めるときは大変だった。

元永区、世話係り、組長
平成20年3月末、すったもんだして5回目の会議でやっと区の執行部が決まり、4月からスタート。
人の良い区長さんをサポートする副区長さん3人に会計2人。
私は広報として「元永区だより」を発行することになった。
元永区制の下に6組の行政組長さん6人×農家を担当する農政組長さん6人の計12名が組長と
兼任した区役員となる分けで、区の役員をしながら組の仕事もする分けだから、仕事は倍になる。
しかも前にも記したように、都会のような町内会ではなく、田舎の町内であるから出事はもの凄くある。
今、この稿を書いているのが7月中旬。
まだ3ヶ月しか経過してないのに、この有様?
それを今からつづって行こうと考えているが、題材はすごく多い。
しかも世話係をやっているうちに結構面白くなってきた!! と感じている。

山の神、神事
春爛漫、桜の季節となった4月5日 「大祖大神社」上の元永山、
山頂で「山の神」神事が行われた。
始めての山頂は県道から250段ほど昇る分けだが、
途中の神社からは石仏を見ながら上がる。
さすがに息切れするが、
80才のおばあちゃんだって山頂の御大師堂や石仏、
観音堂をしょちゅうお参りしているから負けられない。
役員10名が石で祭られた山の神に海の幸、山の幸の、
お供え物を供え、神主が祝詞を捧げる神事は30分ほどあった。

この神事は元永の村が今年も豊作でありますようにという願い事である。
その後、100人ほど集まった区民皆さんと祇園さまで「おこもり」を催した。
いわゆるお食事をしながら皆さんと懇親を図る会のことであり、神社と繋がりを深める為でもある。


元永区神幸祭
おいらの街に祭りがある等聞いてなかった、知らなかった?
と言ったら「それはないでしょう」と近所の人に言われるのが怖い。
区の役員として始めてこの祭に関わることになった。
3週間前から準備が始まり、色々とすったもんだあったが、知らないことは、
関わらないことで済まされるが、イヤおうもなく、無理やり責任を押し付けられた組の当番と役職。
1年間だけと諦めて、ヤルしかない!!
そんなハートが、まさかこんなに熱くなるとは想いもしないことだった。


4月26日(土)夜、大祖大神社境内で汐入りの行事。
役員と神社総代参集の中、神事が始まる。
そして、笛と太鼓の奉楽の中で始まった40分間。
ちょっと想像と違う祭り前夜祭の気分を味わった。


27日(日)は晴天無風。
午前11時より再び神社境内で神事が始まる。
区長、総代、神輿担ぎ手45名他、100名ほど参集した祭り関係者に、それぞれ安全祈願。
そして二体の神輿が若衆達の手から肩に担がれ、
始めて神社境内に出され、100段の階段を降り、元永町内を練り歩く。


汐ふり役の福の神、奉楽の太鼓担ぎ、笛、賽銭箱、鬼、神主と続き、
二体の神輿が祓川河口のお仮場までの道のりを、元永集落人の歓迎を受け、練る。


子供神輿も元気が良い。
私は広報とビデオ、カメラ、交通整理と忙しい。


お仮場で再び神事。
そして神楽興が始まる。
鬼と神主が舞うのだが、これも奉楽の中、実に感動的。

1000年の歴史を誇る神社に、800年続く祭りを見て、
世話をして、ちょっとセンチメンタル的な感激を心の底から覚えた。
午後3時、神輿が神社にお戻りになり、神輿格納庫に収めると夕方6時が過ぎた。
この後、区長宅で懇親会が待っている。
その前に、神輿を担いでくれた若衆、
神楽興の60人のスタッフは公民館で盛大に賑わっている。
深夜10時まで神社総代、区役員、その奥様方と祭りが無事終えた安堵感で祝宴。
皆で喜んだ。


祭りに関連する準備から、終えた後の後始末まで1ヶ月以上
色々大変であったことを付け加えるが、
こんな祭りが毎年繰り返されていることを始めて知った。


松山池開水。用水掃除。田に水を入れる。

米を作る農家の集落に1000年の神社がある
その元永に住みつくことは町人であっても、
その集落の行事に参加しなくてはならない。
5月中旬に用水水路の掃除、草刈り、4つある溜め池と農業井戸2つ、
周辺の草刈りは区民総出で清掃する。
出ないと3000円の出不足金を取られる。
始めて関わるが、やっぱり目が回るほど疲れた!!


掃除と指示と、皆の世話をするから大変だった。
その3日後、平日の朝5時より、池の開水神事から田に水を引く水門の開閉を見て廻る作業。
農民でもないのにする区の仕事。
これが仕事だから仕方がない!!

午前10時に終わり、区長と県の土木課、市の土木課に出向いて、
ガードレールの新設とか、県道の線引き等の願書を届け、話し合い。
これも町内、役員の仕事。昼から出社した。

機関誌 行橋市元永区だより の中でシリーズで紹介しています
シリーズ 元永鎮座・今井津須佐神社のしおり


![]()
私の街には古くからの神社があります。
お正月、除夜の鐘を聞くころ神社にお参りして、
境内でぜんざいを頂けるご褒美で毎年続けている。
普段、縁のない神社には行かないが、
なにがしの願い事があるときだけ通うのがごく普通の人間です。
しかし、元永の皆さんは普段から、この神社との関わりを密にしていたようです。
そのお話しをすると長ーくなりますので、その一部分を紹介することにします。



![]()
私達、元永の氏神様は大祖大神社ですが、
もう一つの須佐神社は北部九州の氏神様で、
この二つが並んでありますから、御両社と言われています。
しかし、心づもりは須佐神社であります。
その須佐神社は、今から755年前の建長6年、
1254年この地に疫病が大流行したので、
地頭職が京都の八坂神社に参り、祇園社を勧請します。
翌年から疫病退散の祇園祭が始まりますが、
その当事より祇園さまと呼ばれるようになります。
たくさんな名前を持つ神社ですが、天暦6年(952年)から、
この地に根付いた伝統ある「元永鎮座、今井津須佐神社」を誇りをもって
子々孫々万年までの加護を願い、篤く信仰されています。


![]()
「いまい ぎおん」で知られる祇園祭りは、
毎年の8月1日、2日、3日に開催されますが、
建長6年(1254年)に京都の祇園社を勧請し、
翌年から祇園祭りを始めました。
その祭りは廿日祇園とも言われ、
内部では7月15日の社頭連歌に始まり、
連日各種の神事が斉行され、最後に大祭である凡そば、
納幣、お八つ撥、連歌、山車から成ります。
最大の見せ場は祇園山車ですが、
今井西の町内で大人の身長ほどもある輪(車輪)に
高さ20mにおよぶ大山車が古式に則り組立てられます。
8月1日夜は提灯山車。
2日夜は山車の上下で笠着連歌。
3日は幟を靡かせて今井の大通りを往復します。



祇園祭、元永山笠復興のご協力、お願い 元永山笠復興会 今井祇園祭は今から753年前の建長6年(1254年)、この地方で疫病が大流行したので、 地頭職らが京都の八坂神社に参り、祇園社を勧請。 翌年から疫病退散の祇園祭がはじまったという伝統の神事であります。 祇園祭の一番の神事は「山笠の巡行」です。 村から悪疫を退散させるため、勇壮な山車が祭りの期間中、村中練り歩くのです。 今井祇園祭では、かつては、曳山四基(今井東町・今井西町・今井中須町・金屋) 舁き山二基(元永・真菰)の合計六基の山が巡行していました。 現在では、今井西町の曳山一基が巡行するだけですが、 元永の舁き山も昭和16年までは祭りに参加していました。 元永の舁き山の高さは15mを超す豊前地方では最大級の山で、 多くの人がかつがないと動かない山でした。 村の繁栄と人々の健康を祈るために長年にわたってかつがれた元永の山。 絶えて久しいこの元永の山を、ぜひ復興させたいとの思いから、 私ども元永の若者有志が集い「元永山笠復興会」を発足させました。 私たちは、まず元永の山の材料探しからはじめました。 山笠の部材は、ばらばらになっていますが、神社境内や区の倉庫に眠っていました。 不足の部材もあるかも知れません。 この部材で山を組み立て、復活させるためには多大な経費と細かな山の情報が必要です。 大きな山笠の復活は大事業です。 ぜひ、あなたも私たち元永山笠復興会にお力を貸してくださいますようお願いいたします。 一、元永山笠の写真、資料などありましたら貴重な情報として活用させて頂きます、お知らせ下さい。 二、行橋の歴史や祭が大好きな方、 私達と一緒に元永山笠復活に力を貸していただける方を募集しています。 ぜひご参加下さい。 元永山笠復興会 事務局 行橋市元永 片山 豊嗣 電話 0930-23-0016 携帯 090-8296-2909 |



元永山笠復興会からのお知らせ 私達、元永山笠復興会は昨年6月の発足から一年が過ぎ、 様々な方面の方からの多大のご協力を得て充実した活動ができました。 昨年の夜祇園では山笠の一部部材の展示をしてみなさんに見ていただきました。 10月は山笠部材確認・部材帳作成・保管場所の確定までたどり着きました。 今年に入っては、元永区氏神(大祖大神社)神幸祭で、 神輿の飾りつけの手伝いや担ぎ手として参加させて頂き、復興会としての役割が見えてきた祭りでした。 また、5月には今井祇園の山笠の流れを汲むといわれる、 犀川の生立八幡の山笠【柳瀬地区】組み立てから解体までの見学及び手伝いをして、 当日の担ぎ手として参加させて頂きました。 そして、今年の夜祇園では、今、残存する部材で組み立てを行い展示しようと計画しています。 組み立ての日時は、7月20日(日曜日)午前8時より作業を行います。 8月2日の夜祇園、私達が子供の頃楽しんだ夜祇園の様に、華やいだ活気のある祭りとして、 私達、元永山笠復興会としても露店を出店して祭りを盛り上げたいと思います。 今井祇園祭は、旧豊前の国でも大変古く歴史のある祭りであります今井の祇園さんは、 京築をはじめ筑豊・筑前・筑後・豊後に数ある祇園社・須佐神社の総社であります。 祇園祭に出ていた山笠も各地に流れていったといわれ、北部九州の山笠の発祥の地とされています。 このままなにもしなければ歴史のあるこの祭りがすたれていきます。 さびしくなった祭りを少しでも盛り上げ、山笠を復活させるだけではなく、 地域活性化につなげていきたいと願っております。 7月20日の組み立ての日には生立八幡の神幸祭のときにお世話になった 犀川柳瀬地区の区長・山笠組み立ての責任者など4名応援に来てもらいます。 その他、元永区役員[数名]・元永神楽同好会の方にも参加して頂き、組み立てを行います。 復興会一同、一生懸命頑張りますので8月2日の夜祇園には是非遊びに来てください。 平成20年7月15日 元永山笠復興会 代表 片山 豊嗣 |
平成20年7月20日 68年ぶり元永祇園山笠復活
元永区に永住する私達は、昭和の初期まで続いていた
元永山笠を今一度見たい、復活させたい、夢、ロマンがありました。



おじいちゃん、おばあちゃんがその昔、今井祇園祭で関わった、
たくさんの夢物語(ストーリー)を想い出話しとして語ってくれたことを、
今の若者達がそれを現実にさせようと必死で努力しています。
平成20年7月20日(日曜日)大安、元永山笠が復活しました。


永久の夢物語が今、現実に再現され、若者達が抱き合い、
感激の涙したこと、この想いを私が独り占めにすることはできません。
区民の皆様には8月1日、2日、3日の祇園さまの参拝の中で元永山笠をご覧いただいて
色々な想い出を再現され、懐かしんでいただきたく思います。


又、元永山笠がこうして現実に再現されていることを元永区ゆかりのたくさんの知人、
お友達に声をかけ、連絡、紹介いただいて、
多くの方々が祇園さまに来て、観てもらいたい、そう思います。
今の若者達が昔の夢物語を受け継いで、もっともっと素敵な今井の祇園さん、
住み良い、楽しみの多い、元永区になるよう、私達は応援したいですね。
「元永区だより」から抜粋


平成20年8月1日
行橋市元永区だより №4 区長 宮崎 一之 行橋市元永区 発行,広報部 上瀧勇哲 |

私達の街には青い空と緑豊かな自然がいつも寄り添って息づいています。
その中で伝統と文化を大切にした、たくさんの人々がいました。
元永の集落には1000年を越える元永鎮座今井津須佐神社があり、
そのお宮を中心にした村人達が豊年、
豊作、健康で幸せな生活を祈願した祭りをするようになります。
建長7年1255年から始まったとされる今井祇園祭は
近隣村人総出によるたくさんの人々が祭りを育みながら、
村の繁栄と人々の健康を祈ること。
そして神社、仏閣を大切にした私達の親交は平和な社会をいつまでも存続させる
温かい心のお祭りであると想います。
おいらの街、元永は
その恵まれた文化を継承しようとする若者達が大勢います。
その若者達を温かく見守りながら元永区の活性と、今からの時代はどうあるべきかを、
問うことが大切ではないでしょうか。
8月1日2日3日の祇園祭には、ぜひ祇園さまに参拝下さい。



今井の祇園さん 元永 夜祇園祭り 平成20年8月1日,2日,3日,
元永の夏祭りは大祖大神社(祇園さま)の夜祇園祭と
8月15日の初盆会(盆踊り)でしょうか。
その準備に追ったくられる私達ですが、
色々な前準備作業は半月前から汗だくで励むのですね。
7月27日(日曜日)は、祇園さまの大鳥居注連しめ縄作り及び張りを行いました。
役員12名が半日かけて作りました。
そして、祇園さまに上がる100段の階段、両サイドにたくさんな提灯が掲げられ、
神社境内は色々な奉納、お札、くじ、販売所が回廊を埋めつくす準備が
氏子の皆様によってできました。
8月1日、今井地区では数百年続く祇園車が引かれ、
私も大勢の中に混じりながら大人の背丈ほどある木型車を引きます。




8月2日(土曜日)、前日から露店が元永通りから祇園さま周辺まで埋めつくし、
午後6時、大勢の人々がお参りにやって来ます。
私は祇園さま周辺の交通規制当番員及び、広報部として忙しく動き回りながら、
賑やかな夜祇園を見て回ります。


元永若衆が独自に店を出した金魚すくいや焼き鳥、カキ氷他数店が大人気。
祇園さま境内も遠来のお客様を招いて神事が続き、境内は賑やかな祭り一色です。


20時、元永神楽舞いがあり、祭りは最高潮になります。
もう人の多さに圧倒されます。




そして午後22時、警察署との取り決めにより閉祭になります。
これは青少年が夜遅くまで祭りにたずさわる事を禁ずる為です。
私達も祭りの後始末をして、深夜23時30分ようやく解散となりました。




元永初盆会、盆踊り 8月15日(金曜日)
今年は区に6軒の初盆家がありますので、
その喪家の方々を招いて合同で初盆をすることが決められています。

その役割を果たす為、私達は半月前から準備を始めています。
もちろん盆踊りの練習もあって、私なりに初体験しました。
8月15日は朝から盆踊り会場作りですが、なんとか13時までに完成。
そして夕方19時より開場です。



喪家の方々により、祭壇に遺影と位牌が置かれます。
その祭壇は奇麗に飾られています。
お参りしてから、区長、喪家代表の方の挨拶後、いよいよ盆踊りです。
子供達や近所皆さんが約200名ほど参集して21時ごろまで踊ります。
ひばり音頭、河内音頭、行橋音頭、元永音頭もありました。
来てくれた子供達にたくさんのご褒美をあげ、21時閉会となります。
喪家の方々に厚くお礼を言われて、なんとか初盆会ができたことを区役員一同ホッとしています。
午後23時30分、やっと帰宅です。



御大師さま盆踊り 8月20日(水曜日)
毎年の8月20日は弘法大師を祭る盆踊りが開催されますが、
以前は元永山、山頂の大師堂前で盆踊りをしていたそうです。
最近は初盆会の会場を利用して、たくさんの方々がお参りしてくれることを願って、
今のようなスタイルになりました。



今年はお天気が良く、浦松みね子先生のお友達皆様他、
浴衣姿のお母様方が素敵な踊りをされて、
例年になく賑やかなほのぼのとした盆踊りがありました。
お大師さま前には小さなお子さまからヤングの皆さん、おじいちゃん、
おばあちゃんが温かく手を合わせる列が続くのでした。


お参りいただいた皆さん、ありがとうございました。


早稲神事と秋のおこもり 平成20年9月6日(土)
そろそろ稲刈の季節になる頃、
秋の「早稲おこもり」が大祖大神社でおこなわれた。
早稲が無事刈入れができ、今年も豊作でした。
その感謝と区民皆さんが健康で過ごせますように、を祈念する為、
大祖大神社にて式典、儀式がおこなわれます。


高辻安仁神主が祝詞をあげ、役員一人一人に
大きなお祓い棒でスッポリかぶせて祈念していただきます。
そのお祓いが終わった後、役員会議。
その後、元永区各組ごとにおこもりが始まります。
お花見弁当を広げていますと、神社からのお神酒が廻ってきたり、
組のお酒が両方からぐるぐる巡ってきます。
お弁当にビールやお茶、菓子等もあって、たいへん賑やかな花見です。
そのような「おこもり」が夕方まで続く組もあります。
午前11時~夕方まで


お大師堂で千願心経 平成20年9月7日(日)
元永村の年中行事として江戸時代から続いている千願心経は、
お大師さま(弘法大師)を祭る一つの行事です。
詳しいことは今から勉強しなくてはならないのですが、
元永山の頂上にあるお大師堂は広さ20畳ほど。
中央にお大師像。
上、中、下段にそれぞれお人形さまの仏像が8つほどあります。
その堂の横には地像堂があり、こちらも10体の観音様から仏像があります。
もう一つの離れた広場にもお堂がありますが、
こちらは石仏のお地像さまが30体ほどあります。
又、元永山山頂には石仏や地像さま、お偉いお坊様石仏が20体ほどあり、
それぞれの箇所に大久保さんご夫婦がお花やシバを供えていました。


私達、「男性役員は山頂の掃除」川口さん、
槌田副区長は元永山山頂に続く階段の手すり竹棒を新しく取り付け、
女性達は大師堂の掃除から飾り付けで汗だくです。
私はヤブ蚊からたくさん食いつかれてカイカイ。
いずれも朝7時から9時までの作業です。
9時前から千願心経のお参りの方が山頂まで登ってこられ、
今日は30名ということで、1000経÷30=34カンのお経を唱えることになり、
10本の木ぎょを叩きながら経をあげます。
大久保さんは腕が疲れた、腰が痛い等々でけっこう皆で
楽しみながらのお経があり、11時30分に終わり。
その後、皆でお弁当を広げ、
お大師さまを偲びながら元永区民皆様のご加護をお願いしたのでした。
午前7時~13時ごろ


1の2組 組長としての心づもり色々
毎週、毎日のように元永区の世話係をしているこの頃ですが、
この稿を書いているのが9月9日、10月に入れば、
なんとか連休日をとって久しぶりに沖縄の釣りをしようかと日本旅行に行ったら、
予定していた日は飛行機の予約が取れなくて残念。
来年にすることに決めました。
6日、7日は前記の行事に加えて、組の方の葬儀があり、受付係等の大役。
それが終わって「敬老会祝い品の配布」は24軒。
「市交通共済会の申込み案内から受付」等を40世帯廻ったり、
来週は今元校区の「朝の挨拶運動」で子供達に「おはよう」等々。
毎日毎日が世話係の日々が今続いています。
敬老の日 9月15日
行橋市より65才以上の老人に敬老お祝い金が頂けることで、
今年は500円ほどの石鹸を今元校区で準備されました。
それをもって私の組12世帯に配布しました。
それにしても、元永区もけっこう老人が多くいます。
いずれ、私もその仲間に加わるのが7年後。
秋の用水、元永区草刈り、水路掃除 9月28日(日)
朝8時から草刈カマを持って、イザ出発。
大祖大神社の水路から松山池までの水路の担当だが、
元永区の農家と区役員は全員協力しなければならない。
私ら夫婦は一週間前よりチラシを配ったり、
川辺生産組長、川口副区長さんと相談しながら、
草刈機の確保や全世帯に電話して出欠の確認。
そして昼の弁当手配や、おやつのパンとかお茶、コーヒーの買出し、
大きなクーラーボックスに氷を二缶買って冷やしたり、
お茶を入れたキーパーの準備等、色々大変です。
そして、お昼まで水路の中に入ってドロまみれ。
昼から役員だけ公園や池、貯水槽の草刈で2時にやっと終わります。
もうクタクタで、昼食の弁当を二人で食べたのが3時30分でした。
◎次の日、参加者名簿を水利の大久保さんに届け、出不足の家に集金。
その次週は出席された農家に御礼金の配布等、組長さんは大変です。
でも、奥様が半分以上してくれて感謝。
藁すぐり 10月12日(日)
毎年のパターンで動いているが、
藁すぐりは農家から稲ワラをもらって藁すぐり機械にかけます。
(ワラをきれいにとくこと)、神社の注連縄を作る為の下地準備をしておくこと。
この作業を昼から5時までかかりました。
区長さんはじめ役員さん全員で、この作業をおこないますが、けっこう大変なんですね。
元永メダカの里、収穫祭 10月19日(日)
「元永土地改良区」が主催するイベントは地元区民と周辺の馬場、
真孤地域が協力して毎年開催されています。
前日の土曜日午前中に私ら夫婦は紅白の餅つき、
餅を袋に入れる作業の加勢、昼食のオニギリまで頂きます。
次の日の本番は多様で参加できませんでしたが、2俵の餅米で餅つき。
イモ掘り。枝豆つみ。イチジク狩り。
魚釣り、メダカ池。餅まき等、多彩な催しがありました。
今元校区文化祭 11月9日(日)
校区とは今井町、元永町、それに金屋、真子、祇園団地を合わせた町で形成され、
今元小学校区域で校区と呼ぶようだ。その区域に今元公民館がある。
祓川そばの公民館を会場にした地域の文化交流として文化祭が開催された。
私達はその下準備と終演後の後始末をする。
もちろん他の区域の役員も多数来ているので、けっこう大がかりな文化祭といえる。
その催しの主なものは趣味の展示会からPR事業、
広場で餅つきからフリーマーケット、採りたての野菜の販売はもちろん、
主婦達が手作りする鍋物の奉仕等、賑やかに催される。
私は会場準備で半日ほど奉仕した。
祇園さま(大祖大神社)注連縄張り 12月23日(日)
もうすぐお正月を迎える年末、祇園さま広場の大鳥居に飾られている
注連縄を新しく取り替えることになり、区役員は全員朝から参集。
直径20㎝、長さ5mほどある大竹に縄を巻きつける作業だが、
けっこう力と技術が必要です。


手馴れた川口副区長が手本を見せて、若い片山さん、
原田さんが縄を編んで巻きつけてゆく作業は上手い。
補佐する、宮崎、岡村、島、槌田、川辺さん、縄を選りすぐって選定する。
堀、大久保さん、私達夫婦もその作業に追われる。



3時間ほどかけて巻き終え、川口さんが最後の締めを手直し、
高辻宮司が作ってくれた御幣を巻き付け、
大鳥居に取り付けるまで4時間かかりました。



この作業をしながら宮司がお神酒の寄贈。
島会計が清酒に缶コーヒーの寄贈で、けっこうほろ酔い調子で
製作した注連縄張りも楽しく過ごせたようです。


元永山山頂、大師堂広場 & 祇園さま参道の清掃美化 12月23日(祭日)



清掃日はあいにくの雨ということで急遽、
23日(祭日)に変更をお願いしました。
当日は肌寒い早朝でしたがお天気も良くなり、たくさんの参加で、
お大師さま周辺から、その参道、
祇園さまの階段も奇麗にしまして、予定より早く終了しました。
今度は1の1組、1の2組、2組、の当番で美化をいたしました。
ご奉仕された皆様、お疲れ様でした。

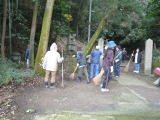
大師堂参道、手すりの修復 12月23日(祭) 午後から
お大師さまがある元永山山頂に登るには、たくさんな階段があります。
その中でも特に急な階段には手すりを取り付けています。
山頂に近い手すりには手作りの木と竹の手すりなので、
支柱が腐るとすぐに倒れてしまいます。
昨年の4月1日に修復しました。
今度も新しく杭を打ち込み、ガッチリ修復いたしました。
毎年、元永山、お大師堂等を管理する元永区は
たくさんな人々の奉仕でなりたっています。


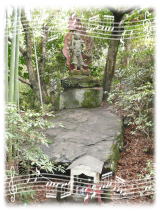

|
|
おいらの街 元永 行橋市元永に引越して 主人の会社が行橋市に変わり、 思い切って母が住む行橋市に住むことになりました。 元永に住まいを構え、緑豊かな田ンボの中の一軒家にチョット淋しい日々がありましたけれど、 隣の畑に毎日通ってくる宮崎のおばあちゃんに 声をかけられて、初めてお友達が出来たのです。 そのおばあちゃんの日課は、畑の野菜作りにカキの木とイチジクの手入れ等、 朝から日が暮れるまでお仕事をしています。 そんなおばあちゃんの畑に入り 「アンタ!! この畑やるけ何か作んなさい」と カキ木そばの畑でトマトやネギ、お多福豆等、植えてくれました。 それからは、おばあちゃんの手伝い等しながら世間話し。 私家の庭でお食事をしたり、とにかく一人ぼっちの私に いつも声をかけてくれる大好きなおばあちゃんでした。 そのおばあちゃんからオコワご飯を良く頂きました。 なんでも祇園さまにお供えしたり、近所に配ったりしているそうです。 そのお母さんみたいなおばあちゃんとは わずか三年ほどでお別れをしました。 今は県道向かいの畑を毎日耕している村田のおじいちゃんから大変可愛がられて、 たくさんの農作物をいつも頂いて、感謝感謝でいっぱいです。   ご近所の皆さまも優しい人ばかりで、お世話になりっぱなしです。 今年は特に組長と区の役員となり、 主人と二人で一生懸命皆様のお手伝いをしながら、 なんとかお正月を迎えることができました。   おかげさまで元永区の歴史とまではいきませんが、 代々伝わっている大切な行事や神社、お寺さま、 そして元永山から見る元永、京都平野を見て改めて元永の良さ、 人々の温かさ、ぬくもりを感じる日々です。 上瀧洋子  |
元永区農道ジャリ入れ散布作業 平成21年2月8日
農道は私達の暮らしに密着した区民の私道でありますが、
農作業に熟知している農家の皆さんにとっては仕事場の一つでもあります。
快適なスピーディな作業を行うためにも、平らな、歩きやすい農道でなければなりません。



そのような整備された道作りは年に数度、農家の皆さんがジャリ入れ作業や、
両サイドの草刈り 及び 水路等にも大変気を使っています。
今度は[元永区資源保全実行委員会]主導で、
元永区全域の農道に数種のジャリ入れ散布をいたしました。
奉仕された皆さまお疲れさまでした。


平成21年3月7日 元永区役員会議 一年間お疲れ様でした。
本年度を締めくくる元永区の定例役員会議は今度で20回目となります。
宮崎区長が、まずテーマを提出し、平成20年度の会計決算報告等を皆さんでまとめたり、
農家の米減反42%とか、水資源や区内の様々な行事を盛り込んだ
会議はいつも午後22時を過ぎています。



元永区の下部組織には6組あり、各組より小組長さん2名と区長さんの13名がお世話係。
その補佐を役員の奥様が色んなところで協力しながら、やっと役目を終えることになりました。
今月の末には新組長さん、
そして新しい区役員さんに引継いで頂いて平成20年度の行事が全て終えます。
一年間お世話された皆さま大変お疲れ様でした。


平成21年3月8日 元永区1の2組 常会(総会)
私の組は戸数39戸、プラス2戸あります。
その20年度を締めくくる常会をいたしました。


色々な
①行事報告
②会計報告
③決定事項(規約の変更)
④元永区からの報告事項
⑤小組長、生産組長、水利委員、神社総代2名の役員決定。
⑥21年度に向けての引継事項
⑦その他 を決めて終演となりますが、参加者皆さんから、お疲れ様でした。
と、熱いねぎらいの言葉を頂いて、
妻ともどもホッとした気分で公民館の戸締りをするのでした。



|
|
平成20年度「行橋市元永区だより」まとめ
都会から元永に移り住んで早8年を過ぎようとしておりますが、
その元永区のお世話係をさせていただいて知る、たくさんな出来事は全て初体験。
民芸文化から神社、仏閣を大切にする区民皆さまの
温かい想いを様々なところから知ることが出来ました。
大切にしないといけないこと。
私達が日常的に頂けるたくさんの農作物を豊かな大地で育てること。
それを支える神社、仏閣は民、区民の心を優しく包み込み、
和らげ、明日の、未来の、希望、夢を与え、諭してくれる。
そのような伝統的な触れ合いを、
民芸とか文化として永久に受け継がれていることを知り、
これからの現実を一歩一歩、歩みながら元永文化を継承してゆけることを望み、
次の方にバトンを渡したいと想います。ありがとうございました。












